レンジローバーって、とてもカッコよくて人気のある高級SUVですが、「どれくらい走れるの?」とか「何万kmまで乗れるの?」と気になる人も多いですよね。
特に輸入車は故障しやすいイメージがあるので、寿命やメンテナンスについて心配になるのも当然です。
今回は、そんなレンジローバーの「走行距離」と「寿命」について、くわしく解説します。
さらに、できるだけ長く乗るためのポイントもまとめて紹介しますので、これからレンジローバーに乗る人も、すでに愛車として大切にしている人も、ぜひチェックしてください。
「走行距離」と「寿命」の関係や、長く乗るために必要なことが分かれば、レンジローバーと安心して長く付き合えるようになります。
高級車だからこそ、しっかりした知識を持っておくことがとても大切です。
ぜひ最後まで参考にして、愛車を長く大切に乗り続けてください。
レンジローバーの走行距離の目安はどれくらい?
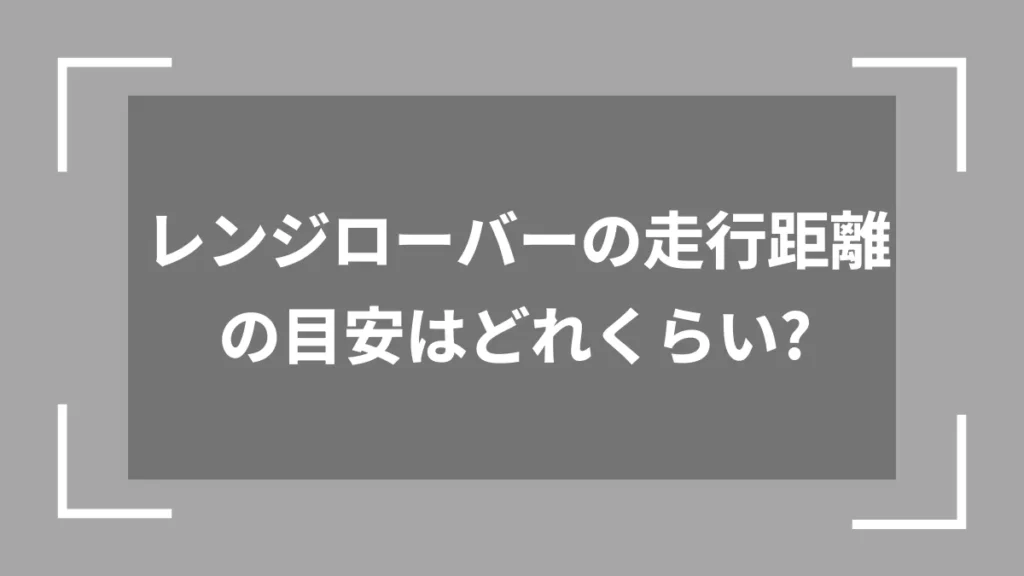
レンジローバーの平均的な走行距離とは
レンジローバーは高級SUVとして知られていますが、実際にどれくらい走ることができるのか気になる方も多いです。
ここでは、レンジローバーの平均的な走行距離について解説します。
- レンジローバーの平均走行距離は、年間で約10,000kmから15,000kmが一般的です
- 日本国内では、通勤や買い物といった近距離移動が中心のため、年間走行距離は10,000km以下の車両も多いです
- 一方、アウトドアや旅行で使用する場合は、年間20,000kmを超えるケースもあります
- 中古車市場では、10年落ちで走行距離10万km前後のレンジローバーが多く流通しています
- 海外では長距離移動が多いため、日本よりも走行距離が多くなる傾向があります
このように、使用環境やオーナーの使い方によって走行距離には大きな差がありますが、レンジローバーの平均的な目安としては「年間1万km前後」がひとつの基準になります。
モデル別の走行距離の違い
レンジローバーには複数のモデルが存在しますが、それぞれのモデルごとに走行距離の傾向は異なります。
ここでは代表的なモデルごとの特徴を解説します。
- レンジローバー(フルサイズ):高級志向のオーナーが多く、走行距離が少なめの傾向
- レンジローバースポーツ:スポーティな走りを求める層に人気で、比較的走行距離が多い傾向
- レンジローバーイヴォーク:街乗りメインのユーザーが多く、年間走行距離は少なめ
- レンジローバーヴェラール:都会的なデザイン志向のユーザーが多く、使用頻度も控えめなケースが目立つ
- ディーゼルモデル:燃費が良く長距離移動が多い傾向で、走行距離はガソリン車より多め
このように、同じレンジローバーでもモデルによって走行距離に違いが出るため、自分が購入を検討しているモデルの傾向を知っておくことが重要です。
ガソリン車・ディーゼル車での差はある?
レンジローバーにはガソリンエンジンとディーゼルエンジンの両方が存在しますが、走行距離にはエンジンタイプによる違いもあります。
- ガソリン車:街乗りや短距離移動に使われることが多く、年間走行距離は少なめ
- ディーゼル車:燃費が良く長距離移動に向いているため、走行距離が多くなる傾向
- ディーゼルエンジンは頑丈で長寿命とされ、20万km以上走る車両も珍しくない
- ガソリン車は静粛性が高く快適ですが、エンジンの耐久性はディーゼルに比べるとやや短い
- 中古車市場では、ディーゼル車のほうが過走行車両が多い傾向
どちらを選ぶかは用途次第ですが、「長距離メインならディーゼル」「街乗りメインならガソリン」が基本の考え方です。
中古車購入時にチェックすべき走行距離のポイント
中古のレンジローバーを選ぶ際は、走行距離のチェックがとても重要です。
以下のポイントを意識して選ぶようにしましょう。
- 10万km以上の車両はメンテナンス履歴を必ず確認
- 走行距離が少なすぎる場合も要注意(長期間放置されていた可能性あり)
- 年式と走行距離のバランスをチェック(極端に少ない・多い車両は避ける)
- 試乗してエンジン音や足回りの異音を確認
- オイル交換やタイミングベルト交換の履歴も重要
走行距離だけでなく、整備状況や使用状況も合わせて判断することで、安心して長く乗れる一台を選ぶことができます。
走行距離が多いと故障リスクは高くなる?
レンジローバーは高級車ゆえに部品精度は高いですが、走行距離が増えるほど故障リスクが高くなるのも事実です。
特に以下の点に注意が必要です。
- サスペンションやブッシュ類の劣化
- エンジンオイル漏れや水漏れ
- 電装系(センサーやスイッチ類)の故障
- エアサスのトラブル
- トランスミッションの不具合
走行距離が多い車は価格が安い傾向にありますが、購入後の修理費用を考慮して選ぶことが重要です。
特に輸入車は部品代や工賃が高くなるため、トータルコストを見据えた判断が求められます。
レンジローバーの寿命はどれくらい持つのか?
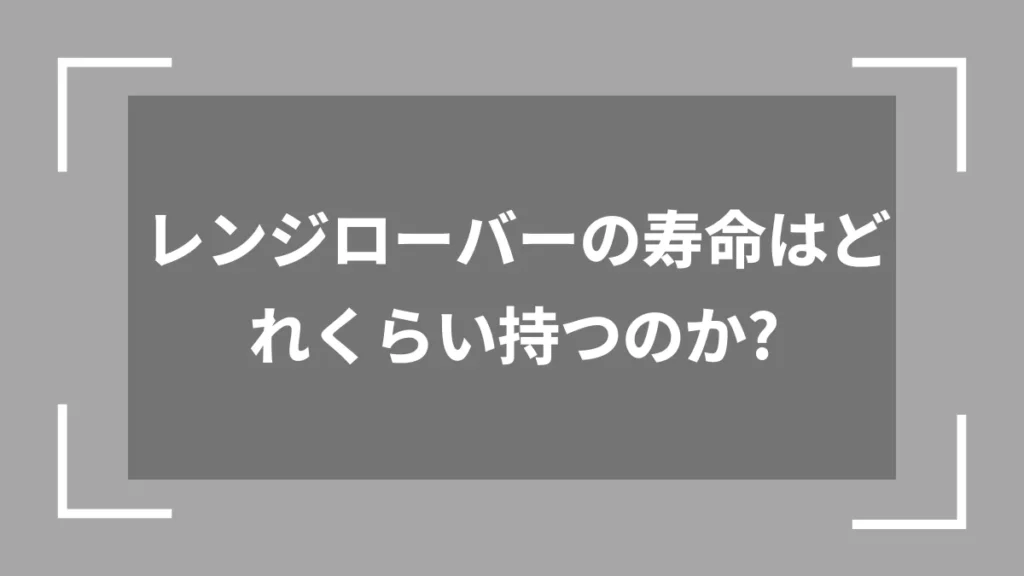
走行距離と寿命の関係
レンジローバーの寿命を考える時、走行距離は非常に重要な目安になります。
何kmまで走れるかによって、買い替え時期やメンテナンス計画も変わってきます。
以下に走行距離と寿命の関係をまとめます。
- レンジローバーは「15万km~20万km」が寿命の目安
- しっかり整備されていれば「30万km以上」も目指せる
- 短距離走行ばかりだとエンジンに負担がかかり寿命が短くなる
- 長距離移動が多い車両はエンジンが安定していて意外と長持ち
- 走行距離が少なくても放置期間が長いと寿命は短くなる
走行距離だけでなく、使い方やメンテナンス状況によって大きく寿命は変わります。
単純に距離だけを見て判断するのではなく、車の状態を総合的に確認することが大切です。
年式による寿命の違い
レンジローバーは発売された年式によっても寿命が変わると言われています。
ここでは年式ごとの寿命傾向について解説します。
- 2000年代前半モデル:シンプルな構造で故障が少なく寿命は比較的長い
- 2010年代前半モデル:電子制御が増え、電装系の故障リスクが高まる傾向
- 2020年代モデル:最新技術が多く使われているが、長期的な耐久性は未知数
- 古いモデルはアフターパーツの供給状況にも注意が必要
- 年式が新しいほど安全性や快適性は向上しているが、電子トラブルが増えやすい
新しいほど安心と思われがちですが、古いモデルのほうが整備しやすく、長く乗れるケースもあります。
年式と寿命は一概に比例しないことを覚えておきましょう。
日本と海外での寿命の違い
レンジローバーは世界中で愛されている車ですが、日本と海外では寿命の考え方が異なります。
ここではその違いをまとめます。
- 日本:10万km超えると「過走行」とみなされ、価値が大きく下がる
- 海外:20万km、30万km走行も珍しくなく、「走って当たり前」という感覚
- 日本は定期車検があり、メンテナンス状態が良好な車が多い
- 海外ではメンテナンスを自分で行うオーナーも多く、整備状況にバラつきがある
- 日本はパーツ代や修理費が高いため、早めに手放す傾向が強い
同じレンジローバーでも、日本と海外では寿命に対する考え方や扱い方が全く違います。
特に輸入車ならではの事情も考慮しておくと安心です。
エンジンや駆動系の耐久性について
レンジローバーの心臓部であるエンジンや駆動系は、寿命を左右する重要な部分です。
これらの耐久性について詳しく見ていきましょう。
- エンジン本体は「20万km以上」持つケースが多い
- オイル管理を怠るとエンジン寿命は一気に縮む
- トランスミッションは10万kmを超えるとトラブルが増えやすい
- 4WDシステムの駆動系パーツも消耗が激しく、定期点検が必須
- サスペンションやブッシュ類は7万km~10万kmで交換目安
エンジンや駆動系は消耗部品の塊ともいえる部分です。
走行距離に応じたメンテナンスをしっかり行えば、長く乗り続けることも十分可能です。
電子部品・電装系の寿命
近年のレンジローバーは多くの電子制御システムを搭載しているため、電装系の寿命も重要なポイントになります。
ここでは電装系に関する寿命について解説します。
- センサー類は5万km~10万kmで不具合が発生しやすい
- パワーウィンドウやスイッチ類は10年程度が目安
- エアコン関連の電装部品は7年~10年で故障リスクが高まる
- 最新モデルは電子制御が増え、故障ポイントが多くなる傾向
- バッテリー管理も重要で、弱ると電装トラブルを誘発しやすい
電子部品や電装系は一度壊れると修理費用が高額になることが多いです。
特に輸入車の電装系は繊細な部分が多いため、予防的な点検が非常に重要です。
レンジローバーを長く乗るためのメンテナンスポイント
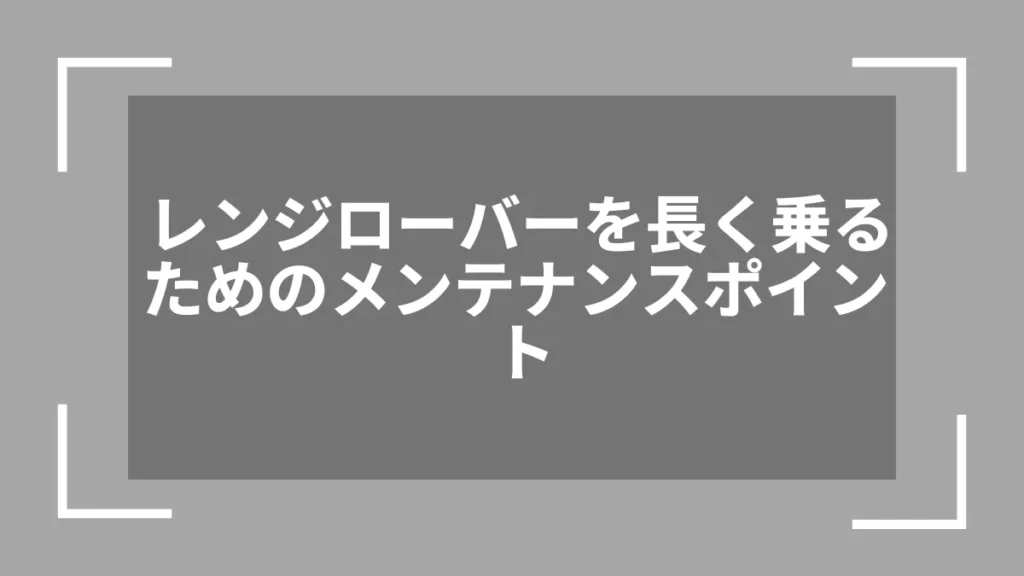
定期点検とオイル交換の重要性
レンジローバーを長く乗るためには、定期的な点検とオイル交換が何より大切です。
特に高性能なエンジンを守るためには、オイル交換をサボると寿命が大きく縮んでしまいます。
- エンジンオイルは「5,000km~7,000km」ごとの交換が目安
- オイルフィルターもオイル交換2回に1回は交換がおすすめ
- オイルは必ず「レンジローバー指定の粘度・規格」を使用
- 定期点検ではブレーキ、足回り、電装系も必ずチェック
- 定期点検の履歴は「記録簿」でしっかり残しておく
オイル交換ひとつとっても、適当に選んだオイルや交換サイクルの遅れが車の寿命に直結します。
特に輸入車であるレンジローバーは、細かいメンテナンスが非常に重要です。
足回りやサスペンションの点検ポイント
レンジローバーは快適な乗り心地が魅力ですが、その乗り心地を支える足回りは消耗しやすい部分です。
定期的に点検し、早めに交換することで長く快適に乗り続けることができます。
- エアサスペンションは「7万km~10万km」で劣化が進みやすい
- ブッシュ類やアーム類も「5万km」あたりでヘタリや異音が出やすい
- タイヤの摩耗や偏摩耗も足回り異常のサイン
- 異音や乗り心地の悪化を感じたらすぐ点検
- 純正部品以外に、強化パーツを使う選択肢もある
足回りは放置すると修理費が一気に高額になります。
早期発見・早期修理が結果的に寿命を延ばす最大のポイントです。
故障しやすい箇所と予防策
レンジローバーを長く乗るためには、「壊れやすい部分」を事前に知っておくことも大切です。
事前に対策をすることで、大きなトラブルを防ぐことができます。
- エアサスのエア漏れ:定期点検でエア漏れチェックが必須
- 冷却系トラブル:ラジエーターやホースの水漏れに注意
- 電装系の故障:センサーやコンピューター系は早めに点検
- オイル漏れ:パッキンやシール類は走行距離とともに劣化
- トランスミッションの異常:ATF交換や定期診断が大切
「壊れやすい」と言われる箇所ほど、定期的にチェックしておけば突然の故障を防げます。
特にレンジローバーは高額修理になることが多いため、事前の予防がとても重要です。
純正部品と社外部品、どちらを選ぶべき?
メンテナンスの際に迷うのが「純正部品」と「社外部品」の選び方です。
長く乗るためには、部品選びも重要なポイントになります。
- 純正部品:品質が安定していて車との相性も抜群
- 社外部品:価格が安く、選択肢も豊富
- 足回りやブレーキなど「走行性能」に関わる部分は純正推奨
- フィルターや消耗品はコストを抑えて社外品でもOK
- 純正部品の供給がストップした場合は、高品質な社外品を選ぶ
必ずしも純正が絶対というわけではありませんが、レンジローバーの場合は「相性問題」が発生しやすいため、重要部分は純正を選ぶのが無難です。
専門店での整備とディーラー整備の違い
レンジローバーを長く乗るためには、どこで整備をするかも非常に大切です。
ディーラーと専門店、それぞれにメリット・デメリットがありますので、違いを理解して選ぶことが大切です。
- ディーラー整備:最新モデルまで対応可能で、専用診断機も完備
- 専門店整備:レンジローバーに特化した知識や経験が豊富
- ディーラー整備:純正部品のみ使用で安心感がある
- 専門店整備:中古パーツやリビルト品を活用し費用を抑えられる
- ディーラー整備:工賃や部品代が割高になりやすい
- 専門店整備:年式の古い車にも柔軟に対応可能
一概にどちらが良いとは言えませんが、「新車保証期間内ならディーラー」「保証切れ後や旧車は専門店」といった使い分けが一般的です。
自分の車の状態に合わせて、信頼できるお店を選ぶことが大切です。
走行距離・寿命に影響を与える乗り方と環境とは?
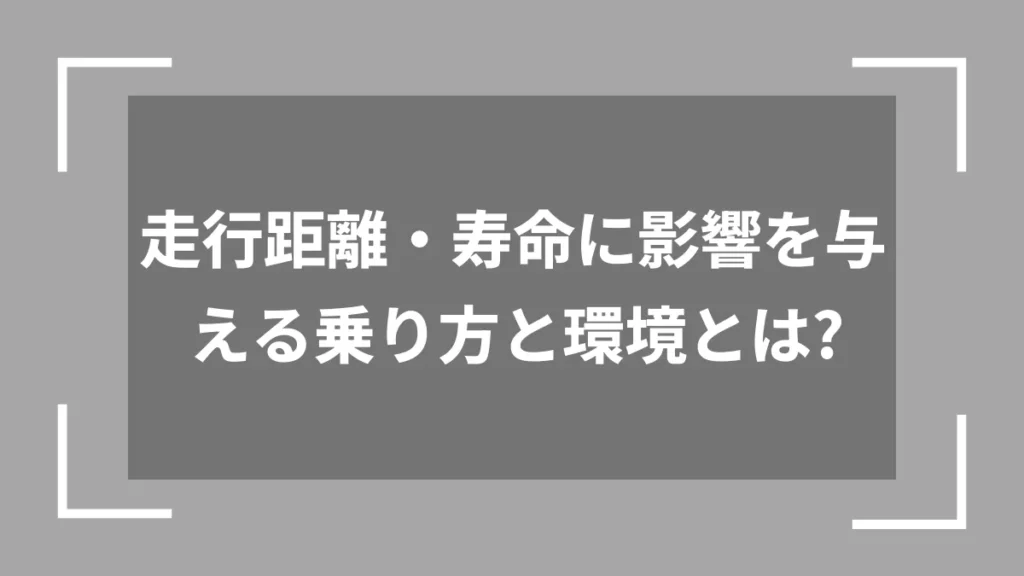
街乗りと長距離走行での負担の違い
レンジローバーの走行距離や寿命は、街乗りが多いか長距離走行が多いかで大きく変わります。
それぞれの走り方による車への負担について、ポイントをまとめます。
- 街乗り中心:エンジンが暖まる前に停止を繰り返すので負担が大きい
- 長距離走行中心:エンジンが温まった状態で一定速度を保つため負担が少ない
- 街乗りはストップ&ゴーが多く、ブレーキや足回りの消耗が早い
- 長距離走行はオイルや冷却水の循環がスムーズでコンディション維持しやすい
- 街乗りではカーボン蓄積が進みやすく、エンジン不調の原因になる
街乗りが多い車ほどメンテナンスの重要度が増します。
逆に長距離走行中心の車両は、意外と良いコンディションを保っていることも多いです。
日本の気候とレンジローバーへの影響
レンジローバーはイギリス生まれのSUVですが、日本の気候が与える影響も無視できません。
日本特有の環境で劣化しやすいポイントを整理します。
- 湿気が多い:電装系に悪影響を与え、接触不良や腐食の原因になる
- 冬季の凍結防止剤:下回りや足回りのサビを引き起こす
- 夏の高温多湿:ゴム部品やシール類の劣化を早める
- 海沿いエリア:塩害によるボディの腐食リスクが高い
- 四季の寒暖差:エアサスなどのシール部分に負担がかかりやすい
日本の気候に合ったメンテナンスを心がけることで、レンジローバーをより長く快適に乗ることができます。
オフロード走行が寿命に与える影響
レンジローバーといえばオフロード性能の高さも魅力ですが、オフロード走行が車に与える負担は決して小さくありません。
寿命への影響を正しく理解しておきましょう。
- 足回りの負担:サスペンションやブッシュ類の摩耗が早まる
- 下回りのダメージ:岩や泥によるキズやサビが進行しやすい
- エンジン・ミッション:傾斜や悪路で無理な負荷がかかる
- 泥や砂:ラジエーターやブレーキに詰まりやすい
- 電子部品:水没や泥汚れでセンサーやカプラーの故障リスクが増える
オフロード走行後は、必ず念入りに洗車と点検を行うことが重要です。
定期的なメンテナンスとセットで考えることで、寿命を短くせずに済みます。
保管環境(屋外・屋内)による差
レンジローバーをどこに保管するかによっても、車の劣化スピードが変わります。
屋外と屋内、それぞれのメリット・デメリットをまとめます。
- 屋外保管:紫外線や雨風の影響で塗装やゴム部品の劣化が早い
- 屋内保管:外的ダメージを防ぎやすく、長期保管にも向く
- 屋外保管:冬季の凍結や霜取りが負担になる
- 屋内保管:通気性が悪いと湿気がこもり、カビやサビの原因になる
- カバー使用:屋外でもボディ保護に有効だが、湿気対策が必要
できるだけ屋内保管が理想ですが、屋外の場合でもカバーや防錆対策をしっかり行えば、大きな劣化は防げます。
過走行車でも長く乗るためのコツ
中古で過走行のレンジローバーを買う場合も、しっかりメンテナンスを続ければまだまだ長く乗ることができます。
具体的なポイントを紹介します。
- エンジンオイルやミッションオイルをこまめに交換する
- 足回りやサスペンションは早めに交換を検討する
- 電装系のチェックを強化して、早期故障を防ぐ
- 冷却系やゴム部品の劣化を見逃さない
- 定期的に専門店で細部までチェックを受ける
過走行車は「消耗品を早めに交換する」という意識が何より大切です。
きちんと手をかければ、まだまだ長く乗ることは十分可能です。
まとめ

レンジローバーの走行距離と寿命について、重要なポイントをまとめます。
長く乗るためのコツもあわせて確認してください。
- レンジローバーの寿命は目安として「15万km~20万km」、整備次第で「30万km」も可能
- 走行距離だけでなく、メンテナンス履歴や使用環境も寿命に大きく影響
- 街乗り中心の車両は劣化が早く、長距離走行中心の車両は意外と良好な状態が多い
- 日本の湿気や凍結防止剤、海沿いなどの環境も寿命に影響を与える
- エアサスや電装系など、レンジローバー特有の故障ポイントは事前に知っておく
- オイル交換や足回り点検など、基本のメンテナンスをしっかり続けることが長寿命のカギ
- 専門店とディーラー、それぞれの特徴を知り、自分に合った整備先を選ぶことも重要
大切な愛車を少しでも長く快適に乗るために、今日からできるメンテナンスや点検を始めてみましょう。
